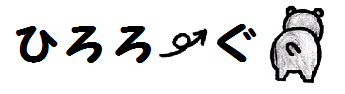2019年の振り返り
平成の30年間が終わり、令和の時代になった。
僕は33歳で、まさに「平成と生きた」人生と言えるが、その時代感をあまり理解せずにここまできたな…と少し反省している。
むしろ、なんとなく、バブル崩壊後の「失われた20年、30年」なんて呼ばれてきたが、社会に出るのが遅かったせいもあって、何が失われたのかよくわからないままにいた。あまり不自由ない家庭に育ったこともあってか、飯が食えないことはなかったし、浪人も、大学生も、留年もさせてもらった。少年時代によくやったテレビゲームは年々進化するし、中学生の時に初めて家にやってきたデスクトップパソコン(Windows95)や、携帯電話、スマホなんかも10数年の間に劇的に進化を遂げた。とにかく、ニュースで流れる不況や悲惨なお知らせはアンテナの外にあって、先人たちが成熟させてくれた社会にずっぽり甘えていた。
一方で、平成は動いていた。阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件、小泉政権の構造改革、民主党政権、リーマンショック、中国の世界工場化、長期安倍政権、TPP参加、米軍基地移設問題、改憲議論、ゆとり教育、少子高齢化…。日本のどこかで起こっている事件・事故、社会問題がいつも社会を賑わせていたはずなのに、自分の足元に目を向けていなければ時間と共に忘れてしまう。
記憶に新しい東日本大震災でさえも、日常の中で埋没してしまいそうになる。2012年に初めて石巻を訪れた時は、被害の爪痕が著しく残っていた。家は基礎以外が流され、船は座礁し、巨大な瓦礫の山が築かれていた。復興屋台村が始まって間もない頃だった。その一年後に松島を訪れた時は、被害などまるで無かったかのような観光地の日常がそこにあった。2015年には仙台空港を利用したが、ここも全く問題なく運航されていた。太平洋沿岸にも日常は戻りつつあるのか…と勝手に思っていたが、2019年10月に宮城県栗原市に訪れた時に、衝撃を受けた。放射能に汚染された山林は利用できず、キノコは原木を他所から買って菌植えしないと販売できないし、東電は十分な保障をしてくれていない。狩猟する人も少なくなり、猪や鹿が田畑を荒らしまわっている。資源利用社会が崩壊しているようだったが、現場にはコミュニティーを活かそうとする人の取り組みを垣間見た。同じ東北の山村に住む身としては他人事に思えなかったし、逆境だけれど今後も地域が繋がってほしいと強く思った。
「あの時のあれは今、どうなっているのか? 」という問いを個々に持ち、調べ、アタックする力が地域で活動するにおいても、求めらているのではないかと思います。
とはいえ、全体として世界は、社会は間違いなく良くなっているんじゃないかなぁと思っています。ごくごく最近まで年金や健康保険なんて存在すらしなかったし、水道やガス、除雪もなかった。障害者に少しずつでも補助できるようになったのも、自家用車が一般に普及するのも、高校や大学に当たり前に通えるようになったのも全部戦後。僕らの生活は農耕革命と産業革命、情報革命の上に成り立っていて、その恩恵を存分に受けながら暮らしています。これら変化の中で保護から漏れてしまった人たちや自然への配慮については、これからを生きる人たちがアタックする課題だと思えば、世代間論争なんてなくなるのになぁ…って思ったりもします。
さてさて、前置きが長くなりましたが、今年自分のやってきたことを振り返りつつ、2020年にやりたいことなどを書き起こしておきます。
2019年にやったこと
大鳥地区の取材&記事執筆を5本
フィールドノートの記録
大鳥も含め、いろんな所で見聞きしたことをiPhoneメモに残していたが、それを大鳥てんごのFacebookページで紹介することを始めた。
<フィールドワークした地域>
山形県鶴岡市山五十川・酒田市飛島・大沢地区・西川町志津・寒河江市田代地区・朝日連峰縦走(朝日鉱泉~大朝日岳~以東岳~大鳥)・東京都奥多摩・青梅市御岳山・東京スカイツリー・新潟県糸魚川市・宮城県栗原市・佐賀市古湯温泉・吉野ケ里遺跡・青森県西目屋村・青森市・弘前市などなど…
糸魚川市や栗原市はジオパーク認定されていて、関係施設があってとても学びやすかった。地質や地形が地域の生活に大きな影響を与えていることを知り、また今年は山形で地震があったこともあって、大鳥の地形・地質に関する情報を集めている。
産総研のシームレス地質図や国土地理院の地図・空中写真閲覧サービスは基礎情報としてとても参考になる。
国交省の重ねるハザードマップも見ましたが、大鳥集落はほぼ全域、土砂崩れに気をつけろ!となってて、「それじゃどうもならんだろ…」って思った。むしろ、過去にどのくらい土砂崩れ、土石流が起こったかという民俗知+ダムによる河床上昇で洪水がどのくらい起きやすくなっているかが気になる。
Sukedachi Creative 庄内の活動
2018年に中間支援の組織を仲間と立ち上げ、2年目の活動となりました。主に山形県内の地域おこし協力隊の後方支援を行っています。とはいえ「人をサポートする」という難しい業務にどう取り組んだらいいのか、模索しながら取り組む日々。幸いにも、一緒に活動しているメンバーにとても恵まれた。みなそれぞれ個性と魅力があって、おもしろい。
日本史の勉強
日本史全般をカバーしつつ、特に、明治~平成を勉強しなおしている。
主な参考図書は、半藤一利の昭和史、半藤一利の昭和史戦後編、小熊英二編の平成史。
民俗調査を始めてから、歴史への興味を持ち直した…(実は、大学受験の時は日本史が得意で、センター試験で92点を取ったこともあった)、というよりは、触れなければ地域の理解が深まらないと思った。目の前にある“かつての暮らし”を眺めるだけでは、“ぬくもりある懐かしい暮らし”しか見えてこない。戦争に駆り出されていく仲間たちも、行政との殺伐とした争いも、『金の卵』の息子娘を見送る眼差しも、国土の開発で切り開かれていく山々も、荒廃していく風景も。それらは地域で起こってきた事実であり、その上に現在の風景と営みがある。
国策に翻弄され、経済に翻弄され、国際関係に翻弄され、それでも大地に根差して生きてきた人々を正しく理解するには、歴史認識が不可欠に思う。
2020年にやること
長期の民俗調査(7月~11月)
以前からじっくり時間を取って日本の歴史や民俗について調査したく、現地へ足を運びたいと思っていました。2020年の7月~11月は大鳥を離れ、関東・中部・関西・中国・九州を車で回る予定でいます。博物館や寺社で日本の歴史を勉強しつつ、個人的な繋がりを頼りながら主に山間地域をフィールドワークしたいと思っています。
なぜ東北以南の山間地域なのかというと、一つはシンプルに雪が降らない地域はどんな環境でどんな暮らしをしているのか、大鳥に似た地域はあるか、現在どんな地域づくりの取り組みをしているのかに興味がある。もう一つは私有林が狩猟活動にどのような影響を与えるかを調べてみたい。雪国では猟期には積雪で土地所有が事実上無力化し、“みんなの山”として機能している。それが、雪が降らず私有林の多い西日本ではどのように機能しているのか、また、それが共同体意識に与える影響も含めて調べてみたい。
また、11月には韓国・中国・台湾あたりも行けたらと思っております。日本の歴史に大いに関係ある施設を巡りたい&息抜きを、と思っています。
具体的にどこへ行くのかは別途ブログで書こうと思いますが、「ここは見ておいたほうがいいよー」とか、「遊びにおいでー!」とか、「ここの宿はおすすめだよー!」とか、ぜひお声がけ頂けると嬉しいです。いろんな方々にご迷惑をおかけすることになるかと思いますが、何卒よろしくお願い致します。
せば、良いお年を。